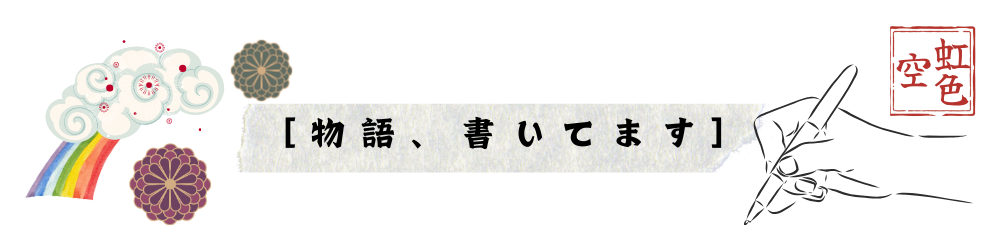冬なのに、花火?
小首をかしげ、彩はスマートフォンを手に窓から外を眺めた。ビジネスホテルの七階からは、すっかり陽が落ちた冬の空と星、都市の夜景、ふわりふわりと綿のように舞う雪が見える。
仁寿からまたメッセージが届いて、ロビーで待っているというので、急いでメイクを直してハンドバッグと部屋のカードキーを手に慌ただしく部屋を出た。無人のエレベーターの中でコートを羽織る。ロビーにおりると、中央にある大きな観葉樹の近くで仁寿が待っていた。
「すみません、お待たせして」
「大丈夫。僕もさっきおりて来たところだよ」
彩は、背高い仁寿の顔を見あげて、全身を観察するように視線をその足元までさげた。ボタンを留めた黒のチェスター・フィールドコートの襟元から覗く、白いワイシャツと青いネクタイ。膝丈のコートの下は、黒いスラックスに磨かれた黒い革靴。そのスラックスも、ビジネス用スーツのそれではなさそうで、どう考えても花火を見にいくような装いではない。それに、私服やスクラブのイメージが定着しているから、スーツ姿はとても新鮮で、急に年を追い越されたような印象まで受ける。
「先生。どうして、フォーマルな格好をなさってるんですか?」
「二十四歳最後の夜に、彩さんと大人のデートをしてみたくて」
「大人のデートですか……。でもわたし、このとおり普通の服装ですよ? 明日の研修医会に着ていくスーツはありますけど、見るからに仕事用だからデートには不向きかもしれません」
「いいよ。彩さんは、そのままで」
「え、でも」
彩の服は、シンプルなニットとスカートにコートを着ただけの普段と変わらないものだ。並んで歩くには、いささか不釣り合いなのではないだろうか。
仁寿が、彩の手から部屋のカードキーを取ってスーツの内ポケットに入れる。二人が今夜宿泊するこのビジネスホテルは、外出する時にわざわざフロントに寄って鍵を預ける必要はない。出張中は、様々な理由でホテルに戻る時間が遅くなったり、頻回に外出したりする。だから彩は、いつも出張の宿泊先を予約する時、チェックインとチェックアウト以外はフロントを通らなくていいホテルを選ぶようにしているのだ。
「そうだ、彩さん。お願いがあるんだけど……」
「なんですか?」
「外で先生って言われると職業をあれこれ推測されそうで嫌だから、名前で呼んでくれない?」
「はぁ……」
目を点にする彩に、仁寿が「お願い」と真顔で迫る。
今まで、医師との出張なんて数えきれないほど経験したのに、呼び方まで気にしていなかった。出張先で街を歩いたり観光をしたり、医師と二人きりでは滅多に業務外のプライベートなお出かけをしないからだろう。稀に、父親くらいと年齢の医師とは美術館に行ったり、女医だと一緒にご当地の有名処で贅沢な食事を楽しんだりするけれど。
しかし、言われてみればそうかもしれない。先生と呼ばれている人を見かけると、教師? 弁護士? お医者さん? などとつい考えてしまうものだ。本人が嫌だというのなら、それに合わせてあげたほうが気兼ねなく過ごせていいのではないだろうか。誕生日だもの、ね。
「分かりました」
「練習する?」
「そうですね。えっと……、ふ、藤崎さん?」
「だめだめ。大人のデートなのに、それだと他人行儀だよ。なんだか疑問形になっちゃってるし」
「さっきと要求が変わっていませんか?」
「変わってないよ。だって僕、名前で呼んでってちゃんと言ったもん」
「あ……っ」
「ね?」
ふふっと仁寿が軽やかに笑う。彩は、ごにょごにょと口ごもって、小さな声で「仁寿さん」と言った。男の人を名前で呼ぶ習慣がないから、すごく恥ずかしい。理由は多分、それだけではないけれど……。
「彩さん、心配しないで。何事も、慣れてしまえばなんてことないからね。それから、今夜は仕事の話はなしだよ」
「は……、はい」
「じゃあ、行こう!」
仁寿が、肘を曲げて右腕を彩に差し出した。今度は、腕を組めといっているのだろうか。彩は、周りを見回して遠慮がちにそっと仁寿の腕に手を添える。
ビジネスホテルの回転扉を通り抜けると、仁寿が腕を解いて彩の手を取った。そして、手の平をぴたりとくっつけて、お互いの指が絡み合うように繋ぐ。外は雪が舞って、吐く息も白い。暖房が効いたホテルを出て体感温度は急激にさがったはずなのに、頬も指先も、外気の冷たさが適度に気持ちよく感じる。彩が手を握り返して顔を見あげると、仁寿が満足そうに頷いた。
中高生でももっと上手に甘えるんじゃないかな。
自分のぎこちなさにいたたまれない気持ちになって、しかしそれを気にしていない様子の仁寿に救われる。
二人は、通りを西に向かって進んだ。
クリスマスが近いからだろうか。煉瓦造りの建物が並ぶブルックリン風の街並みは、街灯と色とりどりのカラー・イルミネーションの点滅で、日常を忘れてしまいそうなほどファンタスティカルで華やかな雰囲気一色だ。
「この通りをずっと行くと大学がある。ちょっと離れてはいるけど、この辺りは友達とよく遊びに来た場所なんだ。街並みが好きでね」
「そうなんですね。懐かしいですか?」
「まだ卒業して一年もたってないから、そこまで懐かしい感じではないかな。でも、当時はここへ来るたびに、いつか彩さんと並んで歩きたいと思っていたから夢みたいだよ」
「……夢みたいだなんて。またそんな大袈裟なことを言う」
「だって、本当なら竹内が彩さんとここに来てたわけでしょ? それがタイミングよく骨折なんて、夢じゃないかって疑いたくもなるよ。しかも、誕生日だしさ」
「ほっぺた、つまみましょうか?」
「いや、遠慮しとく。彩さん、優しい顔して思いっきりつまみそうだもん」
「よくご存じですね」
「僕と彩さんの仲だから」
温厚な仁寿とは対照的な、ラグビーで長年鍛えた肉体が自慢の熱血漢竹内の顔が頭に浮かぶ。確かに、仁寿のいうとおりだと彩は思う。酔っていたとはいえ、屈強なラガーマンがまさか側溝に足を滑らせて骨折するなんて。それも、研修医会の直前になっての出来事だった。
仕事を休むほどではなく、松葉杖をつきながらなんとか研修を継続できているから、それだけが不幸中の幸いだろう。竹内から連絡がきた時、ケガも心配だったし研修もどうなることかと気が気ではなかった。しかし、今夜は仕事の話はしないと約束した。だから、彩は竹内についてはなにも言わなかった。
「あの、せ……。じ、仁寿さん」
「ん?」
「誕生日のプレゼント、なにがいいですか? 渡せる時に渡しておかないと、またしばらく会えないから」
「そうだなぁ。なんでもいい?」
「もちろん、いいですよ」
「うーん。彩さんからもらう初めてのプレゼントだもんなぁ、すごく悩む」
「来年もありますし、そんなに悩まないでください。もっと気軽に考えていただいたほうが、わたしも身構えずに済みます」
「本当?」
仁寿が、歩きながら彩と視線を合わせるように身をかがめる。その顔がとっても嬉しそうで、彩は少し困惑してしまった。特別なことは言っていないのに、イルミネーションみたいに目をきらきら輝かせて、なにがそんなに嬉しいのだろう。
「二十五歳の僕は、今以上にパワフルに生きると思う」
「どういう意味ですか?」
「彩さんが、僕の二十六回目の誕生日もお祝いしてくれるって言うから」
「あ……。わたし、つい来年もなんて言ってしまって。深い意味はないんです。ただ……」
「約束だよ? 来年の十二月九日の夜、僕のために予定を空けておいてね」
小道を渡る歩行者用信号が点滅し始めて足を止める。彩は、仁寿の視線に耐えきれなくなって、ごまかすようにうつむいた。
「いつも前向きに物事を考えるんですね」
「まぁね。特に彩さんに関しては、前向きの前向き。よそ見もしない。五年思い続けた恋の結末はハッピーエンドに決まってるからさ。押してダメならもっと押す、遠慮なくね」
「どこまで本気で言ってるんですか?」
笑みをこぼしながら顔をあげた彩に、仁寿が「全部、本気」と言う。慈愛に満ちたまなざしと表情に、彩はくすぐったさと胸が熱くなるのを感じた。
それからしばらく通りを歩いて、ある建物の前で仁寿が「あっ、ここ」と立ち止まった。全身を深い青にコーティングされた細長い二階建て。エントランスを挟んで左右にあるショーウィンドウには総レースやベルベットのドレスが展示され、軒先に「Le ciel bleu」――青空――と書かれた銅製の看板が掲げられている。それは、ヨーロッパの街並みに建っていそうなおしゃれな外観の洋装店だった。
仁寿が、彩の手を引いて店に入る。ドアのベルがカランと上品に鳴って、モデルのように美しい顔とスタイルの女性が二人を出迎えた。奥で接客をしている店員らしき女性も、テレビから飛び出して来たような美女だ。
「いらっしゃいませ」
「先日お電話した藤崎です」
「藤崎様ですね。ありがとうございます。では、そちらのお連れ様が?」
女性に笑顔を向けられて、彩は肩をすくめて仁寿に目で助けを求める。仁寿が「そうです」と返事をして手を離すと、今度は店員が彩の手を取った。いい匂いのするきれいな手の平に乗った自分の手を見て、彩はただただ恐縮するばかり。これは一体、どういう状況なのだろう。
「彩さんの服を頼んであるから、合わせてもらって」
「え……、あの」
美女に手を引かれ、戸惑いながらあれよあれよという間に奥へ連れていかれる彩に、仁寿が「いってらっしゃい」と満面の笑みで小さく手を振る。店の奥に行くとドアがあって、隣接する部屋に大きな一枚張りの大きな鏡と化粧品がずらりと並んだドレッサーがあった。
「素敵なバッグをお持ちですね」
店員が、彩から預かった青いハンドバッグをドレッサーの横にあるアンティーク調の棚に置く。手術のあと頑張った自分にご褒美として、トレンド・ブランドのお店で様々なシーンで長く使えそうなカーフスキンのバッグを買った。黒や茶などの落ち着いた色ではなくブルー・カラーを選んだのは、爽やかで涼しげで、見ていると心が晴れやかになる青色が大好きだからだ。
「靴を脱いで、こちらにどうぞ」
店員に言われるがまま、絨毯の上にあがって鏡の前に立つ。すると、店員が一着のカクテルドレスを持って来た。チュール生地のノースリーブで、エーラインのスカート部分にビーズ刺繍が施されたかわいいピンクベージュのドレスだ。
それに着替えるよう笑顔で言われ、困惑しながらコートと服を順に脱いでドレスを着る。着替えが終わると、次はドレスと同色のパンプスが出て来た。シルクサテンにジュエルバックルがあしらわれたローヒール。ドレスもパンプスもサイズがぴったりで、彩は鏡に映る自分の姿を見ながら驚きを隠せない。
「藤崎様がチェスターコートをお召しでしたので、同じシルエットのものを選んでみました。いかがでございましょう」
ノースリーブの肩に、店員が黒いコートを掛ける。ドレスの裾が少し見えるくらいの膝上丈のそれを羽織ると、かわいいドレスの雰囲気にクールな印象が加わって、大人かわいいスタイルが出来上がった。コートの上襟につけられた二つのブリリアントストーン・ブローチが、真っ暗な夜空に輝く双星みたいでとてもきれいだ。
「お気に召されましたか?」
よく似合っておられますよ、と鏡越しに言われて、彩ははにかんで首を縦に振る。
「バッグは大きさや色、形なども申し分ございませんので、お持ちのもので大丈夫ですよ。藤崎様のネクタイの色ともお似合いだと思います」
「……はい」
経験上、こういう時にあれこれ話をしたり質問をしたり、感動のままに声をあげたりするのは、品性を疑われて一緒にいる人の恥になる。彩は、店員の言葉の意味を理解できないまま、なんとか気持ちを落ち着けて、さも分かっているように返事をした。
「着て来られた服と靴は、わたくしどもがお預かりして宿泊されるホテルへお届けしておきます」
「ありがとうございます」
「素敵な時間をお過ごしくださいませ」
まるで魔法をかけるかのように店員がほほえみかける。肩に掛けられたコートに袖を通して店に戻ると、ソファーに座っていた仁寿が駆け寄って来た。
店員に礼をいい、仁寿が再び彩の手を握る。店員に見送られて店を出ると、一台のタクシーが二人を待っていた。ロンドンの街から来たようなブラック・キャブだ。それに乗って着いた先は、海沿いに建つ高級ホテルLaule’a(ラウレラ)だった。