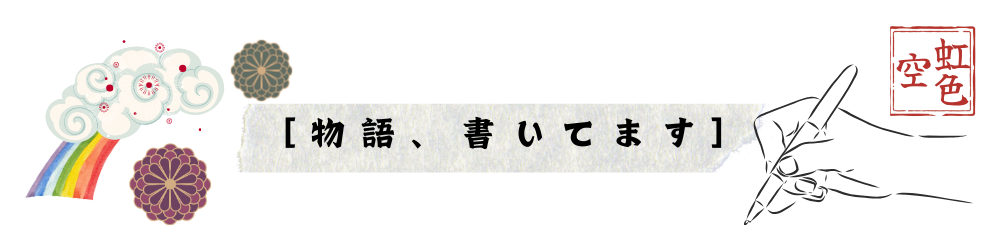「まぁ、ラシュリル。あなたがそんなことを聞くなんて初めてね」
目を丸くしたマリージェの向かいで、ラシュリルは顔を真っ赤にした。
帰国してまだ数日。兄の妃を自室に呼びつけて、お兄様に触れられるとどんな気持ちになるの? だなんて、あまりにも唐突で遠慮のない質問だっただろうか。
マリージェは、キリスヤーナ屈指の名家の令嬢で、幼少のころからカリノス宮殿に出入りしていた。ハウエルの片想いが始まりだった。運命の人だと言って、ハウエルがマリージェを追いかけ回して妃に迎えるまでの一部始終は、今でも貴族たちの語りぐさになっている
ハウエルの純粋で一途な気持ちは、やがてマリージェの心を動かして、二人は誰もが憧れる仲睦まじい夫婦になった。
「ごめんなさい、不躾なことを聞いて。お義姉様なら、笑ったり茶化したりしないで真剣に答えてくれると思ったの」
「嬉しいわ。わたくしを信頼してくれていることも、そういうことに興味を持ってくれたことも」
「そっ、そういうことっていう程のことではなくて、少し……、気になっただけなのよ」
ラシュリルの顔が、ますます赤くなる。マリージェは、にこやかに笑って窓の外に目を向けた。ラシュリルの部屋からは、遠くの海が一望できる。空に広がる灰色の重たい雲と遠洋から迫りくる流氷。キリスヤーナは極寒の季節を迎えていた。
「そうねぇ。一言では言いつくせないのだけれど、とても心が安らぐわ」
「どきどきするのではなくて?」
「もちろん、どきどきもするわよ。けれどね、安心の方が強いの。わたくしの良いところと悪いところ、すべてを受け入れて愛してくださっているのが伝わってくるから」
「……そう」
「他の人では、そうはならないわ」
透き通る青いガラスのような瞳が、まるでハウエルがそこにいるかのように空を見つめている。ラシュリルは、マリージェの横顔にどきっとして見惚れてしまった。
「お義姉様は、いつからお兄様のことを好きになったの?」
「いつだったかしら。初めはハウエル様のお気持ちに戸惑って、素っ気ない言葉を言ってしまったこともあったのよ。けれど、お会いするのが楽しみになって、もっとお話しをしたいと思うようになって、気がついたらハウエル様のことしか考えられなくなってしまったの。魔法をかけられたみたいにね。おかしな話でしょう?」
「おかしくなんてないわ。お兄様もお義姉様も、とても幸せそうだもの」
「ええ、幸せよ。あなたもそういう方と……。運命の人と出会えるといいわね」
「運命の人……」
「そうだわ、ラシュリル。あなたが大好きな苺の果実茶を取り寄せたの」
マリージェが、侍女を呼んでお茶を用意する。キリスヤーナ国王妃の侍女は優秀だ。主人が「あれを」と言っただけで、焼き菓子や飴を手際よくテーブルに並べるのだから。それも、ラシュリルの好物ばかりだ。
「どうぞ、召し上がれ」
「ありがとう、お義姉様。わたし、幸せよ」
「まあ。あなたは、まだまだ恋よりもお菓子ね」
マリージェが上品に声を立てて笑う。
いい香り、と言ってラシュリルは果実茶に口をつけた。ティーカップの中に浮かんでいるのは、夏の間に収穫された糖度が高い古い品種の苺だ。角砂糖を一顆落とした果実茶は、舌がとろけてしまいそうなほど甘い。人肌と同じ温度のティーカップを口元に押し当てて目を閉じれば、重ねた唇の感触がよみがえる。苺の香りよりももっと甘美な、優しいくちづけ。ひと月以上たったのに、昨日のことのように思い出す。
――会いたい。
とても美味しいと無邪気に笑うラシュリルに、マリージェが「喜んでもらえて光栄よ」と温かなまなざしを向けた。
婚儀の三日間、カデュラス国王が王宮を出ることはない。その代わりに、宰相から届いた朝議の議事録に目を通して、王印を押さなくてはならなかった。アユルは華栄殿から戻って、食事をする暇もなく三日分の議事録を黙々と読んでいた。
「アユル様、朝議の時間が迫っております。急いで支度をいたしましょう」
「今日からまた、狸たちと顔を合わせなければならないのか」
「またそのような言葉をお使いになる。なりませんよ、アユル様は尊い身であらせられるのですから」
「分かった、分かった。コルダ様のおおせに従うから、衣をすべて新しいものに替えてくれ。華栄殿の女官が用意したものなど身に着けたくない」
「かしこまりました。では、先にお顔を綺麗にいたしましょう」
アユルが、仰向けに横たわって目をつむる。コルダは、桶の湯で温めた布でアユルの顔を丁寧に拭いて、薄く無精ひげが見える顎に剃刀を当てた。
陶器のようになめらかな白肌に、母親の美しさを受け継いだ貌。アユルの秀麗な姿は、幼いころから王宮に暮らす女人たちを魅了してきた。青年期にさしかかって、アユルのあどけない美しさが男らしさに変化すると、女人たちの関心は次第にマハールからアユルに移っていった。
寝所に忍びこみ、血のように真っ赤な紅を塗った口で慕っているとささやいて、恥じらいもなく衣を脱ぐ。多感な時期に、蜜に群がる虫のような女人たちに夜ごと体を貪られて、アユルは無邪気さと快活さを失った。静かに暮らしたい。コルダが侍従になった時、アユルはそう言って女官を遠ざけた。
「終わりました」
顔の手入れを終えて、コルダが声をかける。コルダは、アユルが立ち上がると手際よく着物を脱がせて新しい衣を着せた。
「今夜はどちらで過ごされますか?」
「私は、掟に従って王妃と三夜共寝した。もう華栄殿に渡る必要はない」
「ですが、アユル様」
コルダは、アユルの冷たい視線に言いかけた言葉を飲みこんだ。遠くで、朝議の時刻を知らせる太鼓が鳴る。
「どうやら、私は父上のようにはなれないようだ。情の湧かない者に触れるなど、耐えられない」
皇極殿では、いつものようにラディエを筆頭に武官文官がひれ伏していた。娘が王妃の座を得たのがよほど嬉しいらしく、エフタルがにたりと笑っているのが見える。アユルが高座に着座したところで、ラディエが顔を上げた。
「陛下。この度は、心より安堵いたしました」
「そうか。皆の気苦労を取り除けたのなら、余も本望だ」
「仲睦まじいお二人の様子も聞き及んでおります」
アユルはうんざりした。ちらりと横目にエフタルを見ると、少し顔を伏せてまだにたにたと笑っている。王妃の体を通して、この男と繋がったかと思うと反吐が出そうだ。これ以上、婚儀の話を続けられても困ると、アユルはラディエの顔を見据えて話題を変えた。
「それで、議事録にあった件だが」
「はい。キリスヤーナ国王より書簡が届いておりますので、陛下にご判断をいただきたく存じます」
「書簡をここへ」
コルダが、ラディエから書簡を受け取ってアユルに手渡す。アユルは、書簡に巻きついた紐を解いて目を通した。
「サリタカルと銅の交易をしたいだと?」
「キリスヤーナでは銅が採れません。国民の暮らしをよくするために、加工しやすい銅を取り入れたいとのことでございます」
アユルは書簡をもう一度読む。書簡には、船の船腹に用いると銅の使い道が細かく書かれていた。キリスヤーナの国民は、大半が短い夏の間に海で漁をして生計を立てていると聞く。書簡のとおりに銅が使われれば、確かに民は喜ぶだろう。だが今、キリスヤーナは極寒の季節ではないのか。
「手に入れてしまえば、あとは好きに使える。なににせよ、あらゆる疑いが排除されなければ、認めるわけにはいかない」
「そのとおりでございます」
「キリスヤーナは、銅を製錬する技術を持っているのか?」
技術がなければ、キリスヤーナとサリタカルの間で銅だけではなく人も動くことになる。今、カデュラスに逆らおうとする国はない。だが、先王の治世を思ってアユルは警戒した。と同時に、一つの可能性を探る。皇極殿の後方から、一人の文官が前に出て頭をさげた。
「陛下、自国では製錬できないのではないかと思います」
「思いますとは、どういうことだ。憶測では、正確な判断ができないだろう。誰か分かる者はいないのか?」
誰一人答えない。アユルは心の内で、無知な官吏たちに感謝した。そして、手順を誤らないように慎重に言葉を選ぶ。
「埒が明かないな。余はどうすればよいのだ、宰相」
「調べます。報告を待って、ご判断ください」
ラディエの返答に、アユルは考えた。脇息に肘をついて、扇を広げては閉じる。臣の最高位にあるラディエを、どう説き伏せようか。四家の一つ、イエサムの当代であるラディエは、王家に忠実で国に誇りを持っている。堕落した先王を擁護し、王の威厳を守るために奔走した男だ。
「このようなことにもいちいち手間取るようでは、実に不甲斐ない王に見えるだろうな」
扇の骨を触りながら、ぼそりとつぶやく。落胆したように肩を落として、科白の最後にため息まで添えると、すぐにラディエが反応を示した。膝を一歩進めたラディエの顔には、明らかな動揺が浮かんでいる。アユルはさらに、やれやれと首を振った。
「陛下のおっしゃることにも一理あるかと。陛下が侮られるようなことがあっては、国の威信にも関わりましょう」
ラディエの横から、エフタルがかしこまった様子で口上を述べた。「ならば、どうする」と、ラディエが険しい顔でエフタルに問う。エフタルが答えに詰まると、官吏たちは真面目な顔で互いに見合って、好き好きに議論し始めた。無い知恵を絞ったところで、妙案など出るはずもないのだが。
「そうだ、宰相。余がキリスヤーナに赴いて、ハウエルの真意と事実を直接確かめるのはどうだ?」
「なんと。陛下の御身になにかあれば一大事です。危険なことをなさらずに、キリスヤーナ国王をここへお呼びください」
「余の身に何事もなきよう、そなたが同行すればよい」
「しかし……」
「心配しなくとも、大臣がいるではないか」
アユルが、意味ありげにエフタルに目配せする。エフタルはごくりと喉元を動かして愛想笑いで応えた。ラディエは、渋い顔でエフタルを見てしばらく思案した。一時的とはいえ、エフタルに宰相の職を任せてもよいのだろうか。若い時から野心家だったエフタルは、アフラムの家督を継いでから一段と地位に執着するようになった。だが、好機でもある。若い王が知識を蓄えて力をつけるのは悪くない。
実のところラディエは、アユルにはマハールのようにはなって欲しくないと思っている。先王が政を投げ出したせいで、臣下の忠誠心は腐敗して、皆が私腹を肥やすことばかりに躍起になった。いくら取り締まっても不正が横行して、目も当てられない状況だ。
「……分かりました。私がお供させていただきます。その間、宰相の務めはエフタルに一任いたします」
「それでよい。これからキリスヤーナ国王に書簡をしたためる。宰相は書簡をあらためて、直ちにキリスヤーナへ送れ」
「かしこまりました」
アユルは、清殿に戻って書斎にこもった。ラシュリルの玉佩を握り締めて、コルダが墨を磨り終わるのを待つ。
「お顔がゆるんでいますよ、アユル様。嬉しいのですね?」
「当たり前だろう」
「墨の用意ができました」
「よし」
鼻歌でも歌い出しそうに、アユルがキリスヤーナ国王へ宛てた書簡を書き始める。さらさらと軽やかに筆を走らせて、仕上げに朱色の王印を押す。書簡は、あっという間に出来上がった。
アユルは書簡を床に置くと、引き出しから手漉き紙を取り出して机上に広げた。もうすぐ会えると知ったなら、さやか花のような笑みで歓迎してくれるだろうか。
意気込んで、勢いよく筆先を紙面に近づける。だが、筆が紙におりない。筆先が何度も紙に近づいては遠ざかる。コルダが不思議そうに見ていると、アユルは筆を置いて肩を落とした。
「コルダ」
「どうなされました?」
「なんと書けばよい」
「書簡でございますか? それならもう、お書きになられたのではありませんか?」
「なんと書けば、ラシュリルは喜ぶ?」
「はい?」
「ああ、私はどうしてこうも間抜けなのだ!」
「ま、間抜け?」
アユルは、絶望に天をあおいで文机に突っ伏す。肝心な時に、気の利いた言葉が一つも浮かんでこない。むくりと身を起こして、書簡を紫檀の軸に巻きつける。それをコルダに手渡して、アユルは咳払いした。
「これを宰相へ届けろ」
「かしこまりました。それで……」
「なんだ」
「よろしいのですか? その、王女様には」
「よい。冷静に考えれば、書簡に恋文を添えるなど言語道断。会って、直接伝える」
コルダが、肩を揺らして笑う。アユルは、コルダをにらみつけて「早く行け」と語気を強めた。
アユルの書簡は、ラディエの手を経て公式な書簡として武官によってキリスヤーナへ届けられた。ラシュリルは、兄夫婦と午後のティータイムを楽しんでいた。二杯目の紅茶に角砂糖を落として、マリージェお手製の焼き菓子に手を伸ばす。
「美味しそうに食べるのね」
「だって美味しいもの。わたし、お義姉様の焼き菓子が大好きよ!」
ラシュリルが、もう一つ焼き菓子を手に取って紅茶を飲む。マリージェは、ラシュリルの笑顔を嬉しそうに見つめた。
「マリージェは、本当にラシュリルのことが好きなんだな」
ハウエルが、やきもちを妬くように口を尖らせる。そこへ、息を切らしたアイデルが駆け込んできた。小柄な老体の肩が大きく上下して、顔は青ざめているようにも見える。
「どうしたんだ?」
「ハウエル様、カデュラス国王より書簡が届きました」
「ああ、僕が銅の交易についておうかがいを立てたからだろう? それで? なんて返事がきたの?」
「大変でございます。カデュラス国王が、直々にキリスヤーナへお越しになられるとのこと!」
「な、なんだって?」
ハウエルが勢いよく立ち上がる。その拍子に、イスが絨毯の上に倒れた。西端の小国が銅を求めても、なんら問題はないはずだ。なのになぜ、カデュラス国王がわざわざこの地へ?
ハウエルは、アイデルから書簡を受け取ると急いで中を確認した。カデュラス国王の直筆で、確かにキリスヤーナへ赴くと書かれている。
――アユル様が……?
ティーカップに添えられたラシュリルの手が、小さく震える。それに気づいたマリージェが、心配して声をかけた。
「ラシュリル、どうしたの?」
「いいえ、なんでもないの。お兄様とアイデルの声に驚いてしまって」
柔らかな唇から、ふふっと軽やかな笑い声がもれる。いいことでも起きたかのようなラシュリルの笑みに、マリージェがきょとんとして首をかしげた。